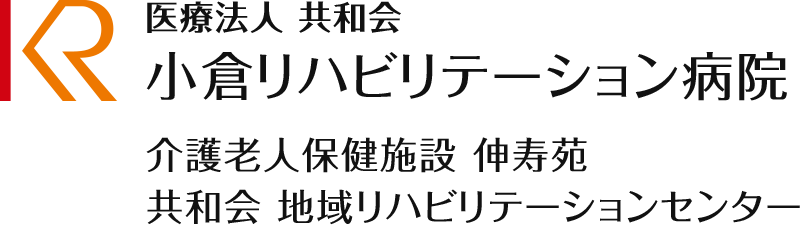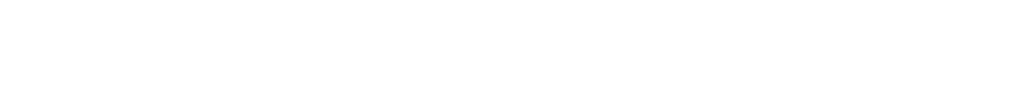当院リハビリテーションの特徴
入院のご案内
トップ/入院のご案内:当院リハビリテーションの特徴
早期自立・安定した在宅生活へ。
回復期から生活期までの総合的リハビリテーション

私ども小倉リハビリテーション病院は、回復期リハビリテーション病棟を中心に、回復期から生活期までリハビリテーションを必要とする患者さまの総合的支援が可能です。また、リハビリテーション科専門医、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、歯科衛生士、管理栄養士などのスタッフを病棟に専従配置し、訓練室のみならず病棟や屋外でもリハビリテーションが効果的に行えるようなチームアプローチを実施しています。
9名のリハビリテーション科専門医
小倉リハビリテーション病院はリハビリテーションの専門病院であり、
リハビリテーション科専門医9名に加え、
整形外科医師、内科医師、外科医師、歯科医師などで業務を行っています。
当院リハ専門医の特徴はリハビリテーション科にて研鑽を重ねた医師の他に、
他診療科経験後にリハビリテーション科へ移られた医師など様々です。
その人らしさを大切に…患者さまにかかわるすべての人と協力しながら診療を行います。
リハビリテーション科専門医は、「疾病の管理」および「障害による身体機能の変化」を病態から考えリハビリテーション治療を行います。同時に患者さまが発症前に行っていた生活を基にその人らしさを大切に、患者さまにかかわるすべての人と協力しながら診療を行います。
すべての患者さまをリハビリテーション科医が担当します。
当院では回復期と生活期のリハビリテーションを提供しています。すべての患者さまをリハビリテーション科医が担当することで専門性の高いリハビリテーションを提供します。
※リハビリテーション科専門医とは
(日本リハビリテーション医学会) 「病気や外傷の結果生じる障害を医学的に診断治療し、機能回復と社会復帰を総合的に提供することを専門とする医師である」

入院から退院に向けた当院のリハビリテーションの特徴
入院当日からリハビリテーションを開始します。
その人らしい暮らしの実現に向けて多職種で協働し、早期に生活リズムの獲得を目指します。
- 県内でも多数のリハビリテーションスタッフが在籍しており、機能回復・向上を目指し集中的なリハビリテーションを行います
- 発症前の生活・役割・人とのつながり、大事にされてきたことなどの理解に努め、目標の実現に向けて、可能性を最大限に引き出せるようリハビリテーションを行います
- 残存機能を生活で最大限に活かすため、病棟生活にもリハビリテーションスタッフは毎日関わります

安心できる・望まれる生活に対し多職種で協議し最善の方法を提案します。
退院後の暮らしの実現に向けて関係者と連携します。
- 退院後の暮らしを見据えて入院中に自宅を訪問し、住宅改修や福祉用具などの提案、リハビリテーションの強化点を計画します。また通い慣れたスーパーや駅などの動線も必要に応じて確認し、これからの暮らしのイメージを深めてリハビリテーションを行います
- 自宅での介助方法や暮らし方についてより具体的に提案します
- 退院後のリハビリテーションを引き継ぐ在宅スタッフや入所施設スタッフ、ケアマネジャーなどと情報共有をします


入院中のリハビリテーションの成果や退院後の暮らしの不安点など目標達成度を確認します。
- 入院中の担当スタッフが訪問したり電話で退院後の暮らしぶりを確認します
- 退院後に新たに発生した困りごとにはその場で対応し、ケアマネジャーとも連携します。退院後の暮らしぶりが安定している場合は、次なる生活目標を一緒に考えます
入院初日から退院までチームでアプローチ
- 入院初日からリハビリテーション開始
- 回復期リハビリテーション病棟は365日入院リハビリテーションを実施
- 入院当日から医師、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、歯科衛生士、管理栄養士が情報共有
- 患者さまの病前の身体機能だけでなく、これまでの人生や役割、周囲とのつながりなどを重要視
- 患者さま本人を中心に関係される方々と早期から連携
専門的なリハビリテーション
- リハビリテーション科専門医の処方に基づいたリハビリテーション
- 医療機器を用いたリハビリテーション(嚥下機能は嚥下造影検査を実施)
- 義肢装具士との連携
- 各種プロジェクトと連携したリハビリテーション
下記のプロジェクトなどとも協力し臨床の質向上に努めています
- 上肢機能プロジェクト
- ドライビングサポートプロジェクト
- 高次脳機能勉強会
- シーティングプロジェクト
- 体力研究会(旧・呼気ガスプロジェクト)
- ロボット研究会
- 運動器リハ勉強会
- 歩行勉強会
生活リズムを早期に獲得するリハビリテーション
- 起床から就寝まで、家庭での生活様式に近いタイムスケジュールで、朝の更衣から人混みを想定した夕方の交通機関の利用などが実施できるリハビリテーションスタッフの勤務体制(早出、日勤、遅出)
- 暮らしを意識した内容・場所でリハビリテーションを実施(病棟でのADL練習や調理練習、病院外でのJRなどの利用練習)

← スワイプしてご覧になれます →
暮らしの再構築に向けた個別アプローチ
- 個々の目標や状況に応じた多職種連携やリハビリテーション
- 在宅生活に向けた具体的な家族指導
- 退院後に必要なリハビリテーションの検討・提案
- 入院前に行っていた活動や人とのつながりを支援(孤立化防止など)
自動車運転の支援体制について
- リハビリテーション科専門医・作業療法士・社会福祉士などと多職種でサポート
- 福岡県安全運転医療連絡協会に参加し自動車運転支援をアップデート
- 福岡県下で統一した項目と判断基準を採用
※外部からのご紹介の場合、内容によっては受け入れが難しい場合もございます。

外来リハビリテーションでの自動車運転支援の実績(令和6年度)
令和6年度は外来リハビリテーションで66名の自動車運転支援を行い、その内、35名の方が自動車学校での実車評価を行いました。外来リハビリテーションでの運転支援を通じて36名の方が運転を再開されました。
運転が再開が難しかった場合には、ご希望があれば、再評価時期を設定し運転評価を継続して実施しています。
[注意事項]
- 当院の外来リハビリテーションでは当院の退院患者さんを中心に支援しております。外部からのご紹介の場合、内容によっては受け入れが難しい場合もございます。
- 当院では運転能力に関する評価のみ行っており、運転の可否に関しては公安委員会(臨時適性検査・臨時適性相談)にて判断が行なわれます。
就労の支援体制について
- 入院・外来リハビリテーションともに就労支援を実施
- 本人・家族・職場の要望に対し、職場面談や訪問による支援を実施
- 就労後も外来リハビリテーションを継続しながら就労状況の確認・対応策を一緒に検討
- 復職が難しい場合には新規就労に向けて支援を継続
- 障害年金や失業保険など社会保障(経済面)に関する相談も実施

就労支援の一部を紹介
通勤方法の獲得に向けた支援
仕事を開始するにはまず安全な通勤が求められます。当院では通勤の手段となる運転支援や公共交通機関利用練習を実施します。
仕事内容に応じた評価(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
職場環境や仕事内容に合わせた動作練習を行います。
職場との連携(面談や訪問など)
医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士などが参加し、作業能力や体力、勤務時間など職場との情報共有をします。
必要に応じて各関係機関と連携
病院でのリハビリテーションと並行し、必要に応じて就労移行支援事業所での職業練習や障害者職業センターでの職業評価依頼・連携など実施し、就労支援を行います。
新たに就労先を検討する場合も各関係機関と連携
就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、障害者能力開発校、就労A型・B型事業所などとも連携し社会参加支援を行います。

北九州障害者しごとサポートセンターでの就労相談の様子