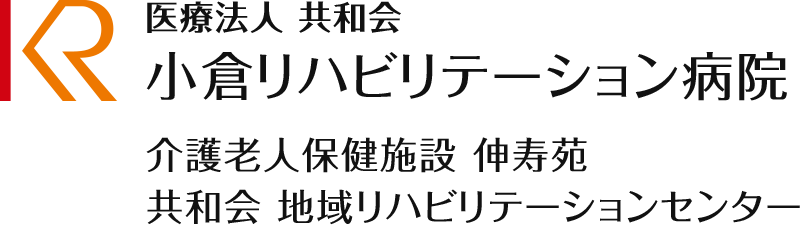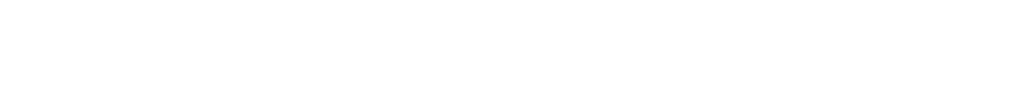病院機能評価
当院について
トップ/当院について:病院機能評価
日本医療機能評価機構認定病院
(財)日本医療機能評価機構より認定
- 2023年2月
- 高度・専門機能:リハビリテーション(回復期)Ver.1.0
- 2025年1月
- リハビリテーション病院 機能種別版評価項目3rdG:Ver.3.0

病院機能評価
「病院機能評価」は日本医療機能評価機構による評価です
患者さんの命と向き合う病院には、その医療の質を担保するために備えているべき機能があります。
国民の健康と福祉の向上に貢献することを目的とする公益財団法人として1995年に設立された日本医療機能評価機構は、病院が備えているべき機能について、中立・公平な専門調査者チームによる「病院機能評価」審査を行い、一定の水準を満たした病院を「認定病院」としています。
評価を行う項目は「患者さんの視点に立って良質な医療を提供するために必要な組織体制」や、「実際に医療を提供するプロセス」、「病院全体の管理・運営体制」など、約90項目があります。信頼できる医療を確保することを目的に、専門調査者が病院の機能を評価することで、その病院の課題を明らかにして医療の質改善を支援するものです。
(公財)日本医療機能評価機構とは
日本医療機能評価機構は、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的に設立された公益財団法人です。質の高い医療を実現するために、病院機能評価をはじめ、医療安全に関する教育研修、医療事故情報のデータベース、診療ガイドライン等の提供など、幅広い事業を実施しています。
小倉リハビリテーション病院は2003年から機能評価機構の認定を受け、今回2025年1月に『 リハビリテーション病院(20~199床)(主たる機能)バージョン3rdG:Ver3.0 』の認定を受けました。また、2019年10月から運用が開始された「高度・専門機能(リハビリテーション)バージョン1.0」の認定も2023年2月に受けました。この高度・専門機能(リハビリテーション)の認定を受けているのは福岡県内でも当院を含めて2病院のみです。
2024年度 小倉リハビリテーション病院受審結果
S「秀でている」… 8項目
A「適切に行われている」… 74項目
B「一定の水準に達している」… 1項目
C「一定の水準に達しているとは言えない」… 0
- S評価項目
- 1.2.2
- 地域の医療機能・医療ニーズを把握し、他の医療関連施設等と適切に連携している
- 1.2.3
- 地域に向けて医療に関する教育・啓発活動を行っている
- 1.4.1
- 医療関連感染制御に向けた体制が確立している
- 1.4.2
- 医療関連感染制御に向けた情報収集と検討を行っている
- 2.1.10
- 抗菌薬を適正に使用している
- 2.2.6
- リハビリテーションプログラムを適切に作成している
- 3.1.4
- 栄養管理機能を適切に発揮している
- 3.1.5
- リハビリテーション機能を適切に発揮している
1 患者中心の医療の推進
1.2 地域への情報発信と連携
1.2.2 地域の医療機能・医療ニーズを把握し、他の医療関連施設等と適切に連携している【S】
〔適切に取り組まれている点〕
連携・広報部に常勤職員を配置して地域連携を推進している。貴院の属する医療圏や地域の特性を分析し、ニーズに沿った自院の取り組み方の検討に活かしている。地域で行われる会合に積極的に参加し、他の医療機関との連携体制の構築に努めている。2022年度からICTを活用した転院調整システムに参画し、これまで6日程度を要していた待期期間を2025年度には3.8日まで短縮しており、地域における急性期病院の病床確保に貢献している点は高く評価できる。紹介元への返書管理では、独自の管理シートを用いて遅滞なく情報が伝えられるよう細心の注意を払っている。年間600件近く行われてた訪問活動(うち、およそ7割に対しては医師が直接訪問)は、新型コロナウイルス感染症拡大により自粛せざるを得ない状況におかれたものの、電話等による地道な情報共有に努めてきた。現在、訪問活動は着実に従来のペースを取り戻してきている状況であり、自院の役割や使命に即した活動が期待されているところである。地域の他の医療機関との良好な連携状況は、高い稼働率にも表れており、地域連携の取り組みは秀でている。
1.2.3 地域に向けて医療に関する教育・啓発活動を行っている【S】
〔適切に取り組まれている点〕
2014年に法人全体の取り組みとして地域包括ケア推進本部を設置し、リハビリテーション医療を核とするさまざまな地域貢献活動を展開している。活動は、「自助・互助活動」、「地域リハ・ケア活動」「連携・ネットワーク」のカテゴリーごとに分けられ、それぞれが推進部会を中心に実践している。2023年度には、小学校での車椅子体験をはじめ、介護予防事業、地域の諸団体と連携したイベントなどに実員数103名、延べ1014名の職員が参加している。これらの活動は、「プロボノ活動」と称する社会貢献活動が基本となっており、参加する職員が自発的に余暇を利用して参加している点は特筆すべきであり、高く評価できる。リハビリテーション・ケアの専門性を指導したり、啓発しようとする考え方ではなく、日頃から実践していることを地域全体で共有すようとする姿勢や企画力、実行力は貴院の理念を象徴するものであり、優れている。
1.4 医療関連感染制御に向けた取り組み
1.4.1 医療関連感染制御に向けた体制が確立している【S】
〔適切に取り組まれている点〕
専従のICDやICNは不在だが、院内感染対策委員会(ICC)と感染の実践チームとしての感染対策リンク委員会(ICT)があり、ICT委員長である医師の指示・指導のもとで非常に活発に感染制御の実践を展開している。医師・看護師・薬剤師・検査技師・理学療法士からなるコアメンバーでの感染サーベイランスやメンバー全員での感染ラウンドを頻繁に実施し、院内での感染の状況を把握し、委員会で検討後に各部署に改善点などを指示している。マニュアルは充実しており、改定も行われている。過去に新型コロナウイルス感染症のクラスターを経験した反省から、医療関連感染制御に向けた体制は細部にわたってルール化されており、多職種が連携しながら実践している点は、高く評価できる。
1.4.2 医療関連感染制御に向けた情報収集と検討を行っている【S】
〔適切に取り組まれている点〕
ICTコアメンバーでの感染サーベイランスやICTメンバー全員での感染ラウンドに加え、毎夕の全病棟報告会で院内の感染の状況を把握し、パンデミック時には保健所や感染ネットワークの上位施設との連携で対策に当たっている。最新の感染状況は職員個々の電子カルテに情報を掲示し、注意を促している。以前よりJANISやJ-SIPHEに積極的にメンバーが関与しており、院内の情報の発信や院外での情報の収集を行っている。また、それらの記録も充実している。感染制御に向けた情報を日々積極的に収集し、対策に活かしている点は、高く評価できる。
2 良質な医療の実践1
2.1 診療・ケアにおける質と安全の確保
2.1.10 抗菌薬を適正に使用している【S】
〔適切に取り組まれている点〕
適正抗菌薬使用指針に準拠し、使用できる抗菌薬は内服6種、注射6種と限定している。届け出制の抗菌薬を使用する際には、院内感染対策委員会と薬事委員会の両者の許可を得てから薬剤を発注するなど管理は厳格である。また、抗菌薬使用中の患者には、感染対策リンク委員長を中心とした多職種による感染者サーベイランスを毎週行い、使用状況や細菌培養結果を確認し、院内感染対策委員会や医局会で報告・検討している。抗菌薬を適正に使用するための仕組みが充実しており、高く評価できる。
2.2 チーム医療による診療・ケアの実践
2.2.6 リハビリテーションプログラムを適切に作成している【S】
〔適切に取り組まれている点〕
主治医による指示・処方のもと、各職種で初期評価を行い、入院1週間目に初回カンファレンスを行い、リハビリテーション総合実施計画書を作成している。その後は、2週間ごとに患者の状態に応じて計画の修正と共有を図り、適宜カンファレンスを開催して、診療計画の見直しを行い、患者や家族に説明し同意を得ている。その際には、単に患者の能力評価だけではなく、「その人らしさ」に重きを置いている。退院後には、訪問や電話連絡を行い、入院中の関わりと振り返りを行っている。入院時から退院後の患者や周辺の環境整備などに絶えず配慮してリハビリテーションプログラムを改変・構築していることは秀でている。
3 良質な医療の実践2
3.1 良質な医療を構成する機能1
3.1.4 栄養管理機能を適切に発揮している【S】
〔適切に取り組まれている点〕
栄養科に管理栄養士6.75人を配置し、調理及び洗浄業務等は委託で運営している。患者の特性や嗜好に応じた対応をきめ細かく行い、アレルギーや禁忌食材に対する完全管理面では、視覚的に注意喚起できるよう食札を工夫し、複数の従事者で確認を行うなど事故防止を徹底している。栄養管理検討委員会で食の質向上を検討しており、嗜好調査や投票によって患者の希望を反映させ、新たなメニューの提供も実現している。選択食を月12回提供しているほか、行事食、各地の郷土料理、誕生日の祝い膳、イベント食など多種多様なメニューを提供しており、アメニティにも配慮した提供体制は模範的水準であり、高く評価できる。HACCPに準拠した衛生管理マニュアルに基づく調理方法を実践し、室温・湿度の管理や床のドライ維持も徹底している。使用食材および調理済食品の2週間冷凍保存や職員の体調管理も法令に基づき適正に行っており、衛生管理全般の取り組みも秀でている。
3.1.5 リハビリテーション機能を適切に発揮している【S】
〔適切に取り組まれている点〕
回復期リハビリテーション病棟と障害者施設等一般病棟の198床ある病院として、154名の療法士で脳血管疾患等、運動器、廃用症候群のリハビリテーションに対応している。1日平均で脳血管7.8単位、運動器6.3単位と全国平均を上回る訓練量を提供している。個々の患者のリハビリテーションの評価は2週毎に見直され、ゴール判定をしている。歩行訓練や日常動作訓練や高次脳機能訓練といった本来の訓練以外にも、今後の人生を考慮した「その人らしさ」を重んじた多職種による全人的なリハビリテーションを展開していることは高く評価できる。退院後も電話や訪問などを駆使して、患者のフォローアップも行っている。業務外で法人のプロボノ活動にも積極的に参加し、地域でのリハビリテーションに貢献していることは高く評価できる。